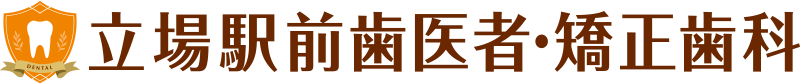子どものすきっ歯が気になる!放置するリスクと治療法
こんにちは。横浜市泉区「立場駅」より徒歩1分にある歯医者「立場駅前歯医者・矯正歯科」です。

乳歯の段階では多くの子どもに見られるすきっ歯ですが、永久歯に生え変わる時期になると「これは治した方がいいのか?」「自然に治るのか?」と、子どもの将来の口元を心配する保護者の方も少なくありません。すきっ歯は審美的な問題だけでなく、将来的な噛み合わせや発音、虫歯・歯周病のリスクにも関係してくるため、放置するのは好ましくないでしょう。
この記事では、子どもがすきっ歯になる原因や放置するリスク、具体的な矯正方法などを詳しく解説します。お子さまの健康な口腔環境を守るために、ぜひ参考にしてください。
すきっ歯とは

すきっ歯は、歯と歯の間にすき間がある状態です。歯科においては、空隙歯列(くうげきしれつ)と呼ばれます。特に、前歯にこのようなすき間があると、見た目に影響を及ぼすだけでなく、発音や噛み合わせにも支障をきたすことがあります。
子どもがすきっ歯になる原因

子どもがすきっ歯になる原因は、必ずしも一つだけではありません。一般的に考えられているすきっ歯の原因を確認していきましょう。
乳歯と永久歯の大きさの違い
基本的に、乳歯は永久歯よりも小さいです。成長に伴って顎の骨も広がり、永久歯が並ぶためのスペースが確保されていきますが、永久歯のためのスペースに乳歯が並んでいる状態では、乳歯が小さいために隙間が生まれます。
この場合、生え変わりが進めば乳歯よりも大きい永久歯に置き換わっていきますので、自然と隙間がなくなっていくケースが多いです。
永久歯の本数が少ない
永久歯は計28本、親知らずを含めると最大32本生えますが、中には生まれつき永久歯の本数が少ない子どももいます。先天性欠如と呼ばれる状態で、何らかの理由で歯が形成されないため生えてこず、その歯の分の隙間が余ってしまいます。
歯並びに影響を及ぼす癖や習慣がある
歯並びに影響を及ぼす癖や習慣があることが原因で、すきっ歯になる子どもも多いです。代表的なものは指しゃぶりでしょう。幼少期の指しゃぶりはごく自然なものですが、4歳頃を過ぎてもやめられないと歯並びに影響を及ぼすことがあります。
ほかにも、舌を前へ出す癖や、舌で前歯を押す癖、口で呼吸する癖などが原因で、すきっ歯になることがあります。
遺伝
すきっ歯になる原因として、遺伝的要素も挙げられます。歯並びそのものが親から子へ引き継がれるわけではありませんが、顎や歯のサイズなどは遺伝の影響を受けます。
そのため、顎が大きく歯が小さいなど、すきっ歯になりやすい特徴を受け継いだ結果、すきっ歯になるお子さまもいます。
上唇小帯の付着異常
すきっ歯になる原因として、上唇小帯が前歯の間まで入り込んでいることも挙げられます。上唇小帯とは、上唇と歯茎をつなぐ筋のことで、通常、歯から数ミリ離れたところに付着します。
これが前歯の間まで入り込んでいると、すきっ歯になる原因となります。成長とともに短縮していくケースもありますが、自然に短くなっていかない場合はすきっ歯が続く可能性が高いです。
子どものすきっ歯を治療したほうがよいか

子どものすきっ歯を治療したほうがよいか判断するのは難しいでしょう。そのため、ここではすきっ歯を治療したほうがよいかについて解説します。
子どもがすきっ歯のままでもよいケース
すきっ歯は、定期的に検診を受けていれば経過観察のみのケースもあります。特に、成長に伴って生じたすきまの場合は、生え替わりが進むと自然に閉じていくことが多いです。
すきっ歯の影響で虫歯のリスクが高まっている、噛み合わせが極端に悪化しているなど、口腔機能に問題がなければ経過観察しても問題ないでしょう。
子どものすきっ歯を治療したほうがよいケース
前歯が上下すべて永久歯に生え変わっているのにすき間が埋まっていない、または、さらに広がっていると感じる場合は、治療する必要があるでしょう。
また、隙間があることで歯磨きがうまくできない、咀嚼・会話が困難になっているなど、機能的な問題を抱えている場合も、矯正治療を検討すべきといえます。お子さまの意見も聞きながら、治療するかどうか考えましょう。
子どものすきっ歯を治療する方法

すきっ歯をどのように治療をするのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。ここでは、子どものすきっ歯を治療する方法について解説します。
矯正治療
歯を移動させて、隙間を閉じる方法です。マウスピース矯正や、ワイヤーを歯の裏側に取りつける矯正方法など、見た目や快適さを重視した方法もあります。
様々な方法が登場していますので、治療内容や期間などを歯科医師と相談しながら検討するのが良いでしょう。
癖の改善
舌癖や指しゃぶりなどの悪習癖が原因ですきっ歯が生じている場合は、それらの癖を改善することも重要です。口周りの筋肉の正しい使い方を学んだり、意識的に癖をやめたりすることで、歯並びが悪化する原因を取り除けます。
上唇小帯の切除
上唇小帯が太く、前歯のすき間に入り込んですきっ歯になっている場合は、上唇小帯の切除を検討します。これにより、前歯が自然と移動して隙間が埋まることもあります。
ただし、上唇小帯を切除しても隙間が残る場合は、矯正治療で歯を移動させて隙間を閉じていく必要があります。
子どものすきっ歯を予防する方法

子どものすきっ歯を予防する方法は、以下のとおりです。
指しゃぶりや舌癖などを改善する
指しゃぶりや舌を前に押し出す癖は、前歯の隙間を広げる原因になります。できるだけ早い段階からやめるように促すことが大切です。
ただし、指しゃぶりは成長過程で現れる自然な行為です。特に、乳児期においては、感覚器官や口周りの筋肉の発達を促す効果があるとされています。そのため、過度に心配する必要はありません。幼児期においても、不安やストレスを感じた際に心を落ち着かせるために行うこともあります。
3歳以降も続くようであれば、歯並びへの影響が懸念されるため、少しずつやめられるように働きかけてあげましょう。
口呼吸を改善する
常に口を開けて呼吸する口呼吸の癖があると、舌の位置が下がり、上顎の成長バランスが崩れる原因になります。鼻炎やアレルギー性鼻炎などで鼻での呼吸がしづらい場合は、まずその原因を改善することが大切です。
耳鼻科での治療に加え、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングも効果的です。口を閉じる意識を持たせるために、日中に軽く口を閉じた状態を保つ練習を取り入れましょう。
歯ぎしりや食いしばりの癖を改善する
就寝中や無意識に行う歯ぎしり・食いしばりの癖は、歯に強い圧力をかけるため歯列に影響を与えることがあります。特に、乳歯から永久歯に生え変わる時期は歯が完全に固定されておらず、隙間が大きくなる場合もあります。
歯ぎしりが見られる場合は、歯科医に相談し、必要に応じてマウスピースの使用やストレスケアを行いましょう。
定期的に歯科検診を受ける
見た目ではわからないような小さな異常や、歯の生え変わり時期の問題も、歯科検診を受けていれば発見できます。早期発見は治療の負担を軽減するだけでなく、予防においても重要な意味を持ちます。
まとめ

子どものすきっ歯は、一時的なものから将来的な噛み合わせの問題まで、さまざまな原因が考えられます。子どもの成長過程において、すきっ歯は自然に改善する場合もありますが、悪影響を及ぼす可能性もあります。お子さまの成長に合わせた適切なケアと治療を行い、健康的な歯並びを目指しましょう。
お子さまのすきっ歯の治療を検討されている方は、横浜市泉区「立場駅」より徒歩1分にある歯医者「立場駅前歯医者・矯正歯科」にお気軽にご相談ください。
当院は、わかりやすい説明と精密でなるべく痛くない治療を提供することを意識しながら、さまざまな診療にあたっています。虫歯・歯周病治療や小児歯科、予防歯科だけでなく、矯正治療などにも力を入れています。